ゼミノート(VOL.5)冨樫あゆみゼミ――学生の“好き”を大切にして、問題意識まで導く!
ゼミを紹介する連載「国際社会学部ゼミノート」の第5弾!
そもそもゼミって?
取り組みたいテーマや教わりたい先生を自分で選び、議論や実践を通して主体的に理解を深めていくゼミは、大学での学びの醍醐味です。
冨樫あゆみゼミ
冨樫ゼミは、朝鮮半島に関するゼミです。冨樫あゆみ先生のご専門は国際政治や安全保障ですが、ゼミでは政治分野に限らず、朝鮮半島に関心を寄せる学生が自分自身の興味を探求する場となっています。ゼミには、韓国のことが大好きな学生がたくさんいます。例えば、K-POPの販売戦略、K-POPアイドルの育成方法、韓国ドラマなどに関心を持って調べている学生もいますよ!
冨樫先生は、学生たちが“好き”、“やりたい”と感じることを大切にしたうえで、それらの興味関心をさらに深めて問題意識につなげ、大学での学びのレベルにまで導いていきます。学生たちは、じっくり時間をかけて自分の興味関心のあるテーマを見つけ、それを読み解いていく方法を段階的に学んでいきます。例えば、ドラマや映画などで取り上げられたことで、韓国は格差社会だということが広く知られるようになりましたが、何が”格差”なのか?どこに要因があるのか?単なる興味関心で終わらせず、深く正しく調べる方法を身に付けていきます。
 |
| 基礎ゼミ(2年生)の様子 |
2年生の学生たちは、自分の関心のあるテーマについて専門書で調べ、読み解く方法を学びます。それを授業内で発表し、最終的にはレポートとしてまとめる、というところまでやっていきます。3年生になると、さらに高度な問題意識までもっていきます。慰安婦や徴用工というような問題について、自分なりに調べ、自分たちならばどのような解決法を示すことができるか、ということまで突き詰めて考えていきます。数週間かけてとことん調べて準備し、自分たちなりの解決策を見つけなくてはならないので、とても良い勉強になります。
このような授業を行うのは、立場の異なる二つの事柄に対して、両者の側にたって考えようとする視点を養ってほしいと考えているからです。日本と韓国の問題では、「真実は一つ」とか、「本当のことを教えていない」ということがよく言われますよね。でも、「真実」とか「事実」と言われるようなことも、その事柄をどのような立場で見るかによって、まったく異なる見え方をすることは多くあります。立場によって、ものの見方は変わるのです。両社会のことを深く学ぶことによって、日韓の関係性について、日本と韓国の両方の視点からわかるようになってほしいと思っています。
冨樫ゼミでは、コロナ前には韓国への合宿も開催していました。合宿では、韓国の大学の日本語学科の学生と交流したり、授業にお邪魔させていただいたりしていました。コロナが収束したら、このような海外でのゼミ合宿も再開できるといいですね。
冨樫先生からメッセージ
学生の皆さんには、自分自身の“好き”を大切にしてほしいなと思います。“興味がある”ということは、大学の学びはもちろん、人生においても、とても大切なことです。好きという感情は人生を豊かにしてくれると思います。自分が何を好きなのか、ということにアンテナを張っていてほしいです。
☞こちらから、冨樫先生へのインタビューを読むことができますよ。
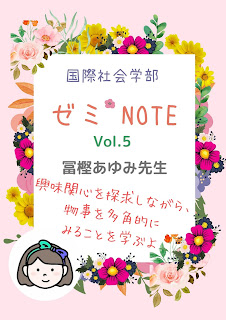











コメント
コメントを投稿